名前変換登録:苗字 名前
苗字:
名前:
カテゴリ「水の都で過ごした」に属する投稿[14件]
サーカスナイト水の都で過ごした#カク #パウリー #ルッチ #フランキー
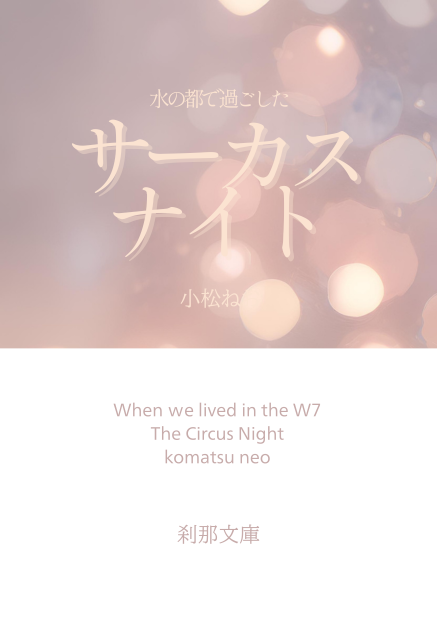
賑やかな夜のこと。
ブルーノの店の前は、今日も人通りが絶えない。
太陽からの支配を逃れた水の都は休む間もなく月の光と瞬く星に覆われる。だが産業都市として、そして世界一の船大工を擁する島として名を馳せるウォーターセブンの夜はさらに眩い。この島は朝も早いが夜も遅い。煌びやかな店々の灯りは、仕事を終えた者たちの頬をつややかに照らし、夜風は酔いのまわった人々の身体をそっと冷やしながら次の店へを誘っていく。あちこちの店から今日の自分を称え、ねぎらう乾杯の音が聞こえてくる。そんないつもと変わらぬ夜のこと。
ブルーノの店の前で、金髪の男と女の子二人組がぶつかり、双方尻もちをついた。
「「どこ見てんだわいな!?」」
「どこ見てんだてめぇ!」
「「「あ」」」
互いにそれはまったく予期せぬことで。
「ああっ! ケーキが!」
「弁償! 弁償だわいな!」
「あァ!? 被害者はこっちだ! 葉巻が全部パーになったぞ!」
「そんな安物……」
「高かったんだよこれは!」
地べたに座り込んだままいい年をした大人たちの子供みたいなやりとりに、一緒にいたルッチとカクは、彼彼女らを見下ろしながら頭を抱えたが、すぐに背を向け他人の振りをした。しかしながら、通り過ぎていく町の人々はそんな『職長三人』を微笑ましく思いながら思い思いに声をかける。
「はは、パウリーのやつまた何かやらかしてるぞ」
「珍しい。相手は女の子だ」
「職長も女の子には頭が上がらないか」
町の人らの適当、いや、的確な物言いにカクはキャップを目深に被り、ルッチはシルクハットを正した。ハットリは何を思ってか、クルッポーと鳴く。
今日は賑やかな夜だった。月は穏やかに微笑み、星はからからと笑い声をあげている。
「キウイちゃんもモズちゃんも、相変わらずセクシーだねえ」
喧噪のどこからか聞こえてきた声に二人は、ありがとうだわいな! と素直にお礼を言った。野次でようやく二人のファッションに気が向いたパウリーが、なんちゅう格好だ!と今さら嚙みついた。肌を出し過ぎだと顔を真っ赤にして怒鳴り散らすパウリーをからかうように、二人は綺麗な長い足を、くびれた腰を、なだらかな肩のラインを、形のいい胸を見せつけながらすっと立ち上がる。いつの間にか集まった野次馬から歓声が上がり、パウリーは地面に尻をつけたままさらに声を荒げた。
「ちょっと待つんだわな、モズ」
女の子の一方が金髪の顔をじっと見つめてはたと何かに気づいたように、もうひとりの女の子に声をかけた。モズと呼ばれた彼女は不思議そうに、自分によく似た女の子の顔を覗き込む。視線がかち合ったのを合図に、ずれた眼鏡を直しながらどうしたんだわいな? と問う。
「この男、よく借金取りに追われてる」
「ああ、ガレーラの破廉恥一文無し」
「おかしな通り名で呼ぶな!」
言いながら立ち上がり二人に歩み寄るパウリーだが、彼女たちは全く怯まない。
「こんな永遠の一文無しから弁償されるなんて、フランキー一家の恥だわいな」
「確かに……危ないところだったわいな」
「人の話を聞け!」
女の子二人にいいように翻弄されているパウリーに呆れ果てていたカクとルッチも、そろそろいいだろうとパウリーを宥めにかかる。
「まあまあパウリー、こんな若い嬢ちゃんたちにそんなに食って掛かるな」
『どっちが年上なんだか』
「あ、山ザル!」
「あ、ハト男!」

「だれがじいさんじゃ! わしは二十三じゃ!」
「説得力はまるで皆無なんだわいな」
「ねえ、キウイ。これ、ハトがいなくなったら喋れなくなるんだわいな?」
『や、やめろ!』
「図星なんだわいな! やっちまうんだわいな!」
今日は賑やかな夜だった。溶けた喧騒が漂い、周囲に霧散した。カーニバル、サーカス、ダンスパーティー。世界中の楽しいものがここに集っていたかのような夜だった。笑い声が零れ、笑顔があふれる。
「ちくしょう! あいつら何やってんだ……」
開いたブルーノの店のドア。聞き馴染んだ声に振り向いたのはモズとキウイの二人だった。
「「アニキ!」」
店の賑わいを背負って出てきた男にキウイとモズが駆け寄る。
「なんだお前ら、ここまで来ておいて……店の目の前で何やってんだ」
「実はあのガレーラの破廉恥と」
「一文無しと」
「店の前でぶつかってしまったんだわいな」
「なんだと!? 怪我はねぇのか?」
「あたしらは大丈夫だけど」
「ケーキが」
アニキと呼ばれた男はサングラスを額までくい、とあげ、キウイが持っていた箱の中のケーキを見やる。ケーキは些か無残な姿ではあった。
「なあに、お前らが悪くねえのは百も千も万も承知! 甘くてうまそうじゃねえか! さあ、さっさと入りな」
「さすが」
「アニキなんだわいな!」
女の子たちはもう、職長たちのことはそっちのけだ。拳をつくり、わなわなと震えているパウリーに男はこうも言った。
「うちのが世話かけたな。一文無しなんだろ? 奢ってやるからお前らも入りな」
拳が解けた。パウリーはさっきまでの勢いをにわかに失い、そこまで言うなら、と店に入っていこうとする。カクとルッチは、プライドはないのかと肩に手をかけそれを止めたがパウリーが振り向いてこう言う。
「飲むんなら人数が多い方が楽しいに決まってるだろう!?」
それを聞いた二人は顔を見合わせ、ふっと笑った。
仕方がないと三人で入店する。
賑やかな夜のことだった。
おしまい
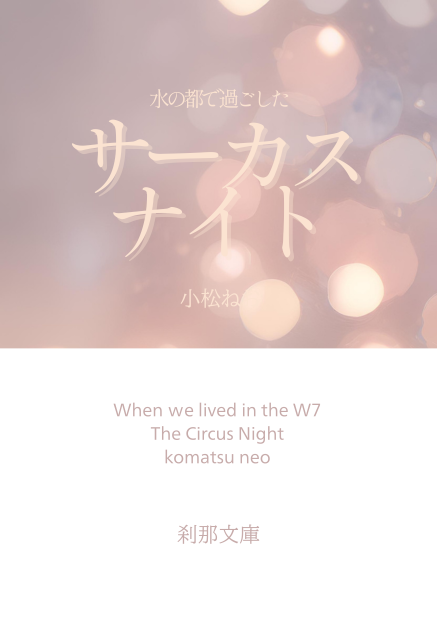
賑やかな夜のこと。
ブルーノの店の前は、今日も人通りが絶えない。
太陽からの支配を逃れた水の都は休む間もなく月の光と瞬く星に覆われる。だが産業都市として、そして世界一の船大工を擁する島として名を馳せるウォーターセブンの夜はさらに眩い。この島は朝も早いが夜も遅い。煌びやかな店々の灯りは、仕事を終えた者たちの頬をつややかに照らし、夜風は酔いのまわった人々の身体をそっと冷やしながら次の店へを誘っていく。あちこちの店から今日の自分を称え、ねぎらう乾杯の音が聞こえてくる。そんないつもと変わらぬ夜のこと。
ブルーノの店の前で、金髪の男と女の子二人組がぶつかり、双方尻もちをついた。
「「どこ見てんだわいな!?」」
「どこ見てんだてめぇ!」
「「「あ」」」
互いにそれはまったく予期せぬことで。
「ああっ! ケーキが!」
「弁償! 弁償だわいな!」
「あァ!? 被害者はこっちだ! 葉巻が全部パーになったぞ!」
「そんな安物……」
「高かったんだよこれは!」
地べたに座り込んだままいい年をした大人たちの子供みたいなやりとりに、一緒にいたルッチとカクは、彼彼女らを見下ろしながら頭を抱えたが、すぐに背を向け他人の振りをした。しかしながら、通り過ぎていく町の人々はそんな『職長三人』を微笑ましく思いながら思い思いに声をかける。
「はは、パウリーのやつまた何かやらかしてるぞ」
「珍しい。相手は女の子だ」
「職長も女の子には頭が上がらないか」
町の人らの適当、いや、的確な物言いにカクはキャップを目深に被り、ルッチはシルクハットを正した。ハットリは何を思ってか、クルッポーと鳴く。
今日は賑やかな夜だった。月は穏やかに微笑み、星はからからと笑い声をあげている。
「キウイちゃんもモズちゃんも、相変わらずセクシーだねえ」
喧噪のどこからか聞こえてきた声に二人は、ありがとうだわいな! と素直にお礼を言った。野次でようやく二人のファッションに気が向いたパウリーが、なんちゅう格好だ!と今さら嚙みついた。肌を出し過ぎだと顔を真っ赤にして怒鳴り散らすパウリーをからかうように、二人は綺麗な長い足を、くびれた腰を、なだらかな肩のラインを、形のいい胸を見せつけながらすっと立ち上がる。いつの間にか集まった野次馬から歓声が上がり、パウリーは地面に尻をつけたままさらに声を荒げた。
「ちょっと待つんだわな、モズ」
女の子の一方が金髪の顔をじっと見つめてはたと何かに気づいたように、もうひとりの女の子に声をかけた。モズと呼ばれた彼女は不思議そうに、自分によく似た女の子の顔を覗き込む。視線がかち合ったのを合図に、ずれた眼鏡を直しながらどうしたんだわいな? と問う。
「この男、よく借金取りに追われてる」
「ああ、ガレーラの破廉恥一文無し」
「おかしな通り名で呼ぶな!」
言いながら立ち上がり二人に歩み寄るパウリーだが、彼女たちは全く怯まない。
「こんな永遠の一文無しから弁償されるなんて、フランキー一家の恥だわいな」
「確かに……危ないところだったわいな」
「人の話を聞け!」
女の子二人にいいように翻弄されているパウリーに呆れ果てていたカクとルッチも、そろそろいいだろうとパウリーを宥めにかかる。
「まあまあパウリー、こんな若い嬢ちゃんたちにそんなに食って掛かるな」
『どっちが年上なんだか』
「あ、山ザル!」
「あ、ハト男!」
「だれがじいさんじゃ! わしは二十三じゃ!」
「説得力はまるで皆無なんだわいな」
「ねえ、キウイ。これ、ハトがいなくなったら喋れなくなるんだわいな?」
『や、やめろ!』
「図星なんだわいな! やっちまうんだわいな!」
今日は賑やかな夜だった。溶けた喧騒が漂い、周囲に霧散した。カーニバル、サーカス、ダンスパーティー。世界中の楽しいものがここに集っていたかのような夜だった。笑い声が零れ、笑顔があふれる。
「ちくしょう! あいつら何やってんだ……」
開いたブルーノの店のドア。聞き馴染んだ声に振り向いたのはモズとキウイの二人だった。
「「アニキ!」」
店の賑わいを背負って出てきた男にキウイとモズが駆け寄る。
「なんだお前ら、ここまで来ておいて……店の目の前で何やってんだ」
「実はあのガレーラの破廉恥と」
「一文無しと」
「店の前でぶつかってしまったんだわいな」
「なんだと!? 怪我はねぇのか?」
「あたしらは大丈夫だけど」
「ケーキが」
アニキと呼ばれた男はサングラスを額までくい、とあげ、キウイが持っていた箱の中のケーキを見やる。ケーキは些か無残な姿ではあった。
「なあに、お前らが悪くねえのは百も千も万も承知! 甘くてうまそうじゃねえか! さあ、さっさと入りな」
「さすが」
「アニキなんだわいな!」
女の子たちはもう、職長たちのことはそっちのけだ。拳をつくり、わなわなと震えているパウリーに男はこうも言った。
「うちのが世話かけたな。一文無しなんだろ? 奢ってやるからお前らも入りな」
拳が解けた。パウリーはさっきまでの勢いをにわかに失い、そこまで言うなら、と店に入っていこうとする。カクとルッチは、プライドはないのかと肩に手をかけそれを止めたがパウリーが振り向いてこう言う。
「飲むんなら人数が多い方が楽しいに決まってるだろう!?」
それを聞いた二人は顔を見合わせ、ふっと笑った。
仕方がないと三人で入店する。
賑やかな夜のことだった。
おしまい
赤を足していく #カク #パウリー
「お前、これ意味あるか?」
「意味?」
休日、暇を持て余してカクの部屋を訪れたおれは、物の少なさに驚きつつも、これでこそこいつの部屋だ、と納得した。自分の部屋と間取りはそう変わらないはずなのに、がらん、という音すら聞こえそうなほど広く見える。物が少ないせいか、ちょっとした音がやけに反響してデカく聞こえるような気さえする。
そんな部屋の壁にかかっているカレンダーはかなり目立ち、かつ意外だった。
「納期しか書いてねェ」
「納期は忘れたら困るじゃろ」
カレンダーはあるくせに、東側の窓には薄いカーテンすらない。朝日は眩しくないのか、と訊けば、別に明るくても寝ていられる、と些か不思議そうだ。カクにはたまにこういうことがある。浮世離れ、とでも言うのか、単に少々変わり者というだけか。
休日だというのに仕事でもしていたのか、テーブルの上には今手掛けている船の図面が広げられていた。所々、赤鉛筆で書き込みがしてある。
「カレンダーにはこういうのを書いとくんだよ」
テーブルに転がっていた赤鉛筆で今日の日付に赤く丸をつけた。赤鉛筆が、シュッ、とカレンダーに走る音が気持ちいい。そのまま『PM20:00 ブルーノの店』と書き入れていくと、訳が分からないという顔で黙って見ていた部屋の主が、それは忘れとらんし忘れても困らんじゃろ、と不服そうだ。
忘れてねェんだな、とは言わなかった。前半にはただ笑って、後半にだけ、おれが困るんだよ、と返事をする。カクもそうか、と笑った。静かな部屋に響く笑い声は、そう悪いものでもないだろう。約束の二十時までこのまま居座ってくだらない話をしてやろうと決め、おれの椅子はどこだ? とカクに尋ねる。
おしまい
「お前、これ意味あるか?」
「意味?」
休日、暇を持て余してカクの部屋を訪れたおれは、物の少なさに驚きつつも、これでこそこいつの部屋だ、と納得した。自分の部屋と間取りはそう変わらないはずなのに、がらん、という音すら聞こえそうなほど広く見える。物が少ないせいか、ちょっとした音がやけに反響してデカく聞こえるような気さえする。
そんな部屋の壁にかかっているカレンダーはかなり目立ち、かつ意外だった。
「納期しか書いてねェ」
「納期は忘れたら困るじゃろ」
カレンダーはあるくせに、東側の窓には薄いカーテンすらない。朝日は眩しくないのか、と訊けば、別に明るくても寝ていられる、と些か不思議そうだ。カクにはたまにこういうことがある。浮世離れ、とでも言うのか、単に少々変わり者というだけか。
休日だというのに仕事でもしていたのか、テーブルの上には今手掛けている船の図面が広げられていた。所々、赤鉛筆で書き込みがしてある。
「カレンダーにはこういうのを書いとくんだよ」
テーブルに転がっていた赤鉛筆で今日の日付に赤く丸をつけた。赤鉛筆が、シュッ、とカレンダーに走る音が気持ちいい。そのまま『PM20:00 ブルーノの店』と書き入れていくと、訳が分からないという顔で黙って見ていた部屋の主が、それは忘れとらんし忘れても困らんじゃろ、と不服そうだ。
忘れてねェんだな、とは言わなかった。前半にはただ笑って、後半にだけ、おれが困るんだよ、と返事をする。カクもそうか、と笑った。静かな部屋に響く笑い声は、そう悪いものでもないだろう。約束の二十時までこのまま居座ってくだらない話をしてやろうと決め、おれの椅子はどこだ? とカクに尋ねる。
おしまい
三百三十六回目の太陽 #カク #パウリー #ルッチ
あと、三百六十五回。
「カクー!」
帰路につこうとしていたそのとき、この四年で聞き馴染んでしまった声に名を呼ばれた。声の調子で酒の誘いだろうとわかる程度には、馴染んだ。今日は疲れているのに、と渋々振り返ればもちろん知った顔だったし、次に続く言葉もやはり。
「飲みに行くぞ!」
だった。しかし、歯を見せ陽気な男の隣に仏頂面の長髪男がいたのは予想外だった。そいつとその肩に乗るハトは、まさか断るつもりか貴様、と表情だけで圧をかけてくる。
ああ、疲れていたのに。読みたい本があったのに。さっさとシャワーを浴びて寝るのも良いし、アルコールよりはコーヒーがよかった。洗濯だってたまっているし、明日も早い。それなのに。
「仕方ないのう」
という答えしか持ち合わせていない自分を呪った。それを聞いたパウリーが、よし! 決まりだな、歯を見せて笑い、先に立って歩く。その背中を追うように、家とは真逆の方向に重い足を引きずった。
「ところで金はあるのか?」
店は相談せずとも決まり切っていたので、三人とも同じ方向に歩を進めていた。夕陽はぐっと傾き、これから始まる夜の賑わいが顔を出し始めている。昼の騒がしさとは違う夜の浮ついた空気は実を言うと好ましく感じているが、口に出したことはない。
「おう、今日は勝ったからな!」
「今日『は』。相変わらずじゃのう」
『懲りないやつだ、ポッポー』
「うるせえな! 勝利の宴だってのに水差すんじゃねえよ」
パウリーが肩に回してくる腕の重さがやけに煩わしい。そもそも、この男は体温が高いのだ。触れている部分がじんわり熱を帯びていくのが鬱陶しくてじろりと睨むが、当の男はこちらの不機嫌さは露知らず。能天気に笑っていた。
気づかれぬように深くため息をつく。そうだ、こういう男だった。
足元から伸びた長い影は三人分くっついて一つの大きな生き物にみえた。好き勝手にくねくねと動くそれは、一部は自分の影なのに自分の意志とは違う動きをしているように見える。影は随分楽しそうだ。思ってすぐ、くだらない、と一蹴する。
「ええい、暑苦しい!」
『同感だ。さっさとこの腕を下ろせ』
「つれねェやつらだな! 今日は誰が奢ってやると思ってるんだ」
軽口をたたきあっている間に太陽は呆気なく沈んだ。あと三百六十五回。三百六十六回目の太陽はここでは見ない。だが、それまでは。きっと隣で。
おしまい
あと、三百六十五回。
「カクー!」
帰路につこうとしていたそのとき、この四年で聞き馴染んでしまった声に名を呼ばれた。声の調子で酒の誘いだろうとわかる程度には、馴染んだ。今日は疲れているのに、と渋々振り返ればもちろん知った顔だったし、次に続く言葉もやはり。
「飲みに行くぞ!」
だった。しかし、歯を見せ陽気な男の隣に仏頂面の長髪男がいたのは予想外だった。そいつとその肩に乗るハトは、まさか断るつもりか貴様、と表情だけで圧をかけてくる。
ああ、疲れていたのに。読みたい本があったのに。さっさとシャワーを浴びて寝るのも良いし、アルコールよりはコーヒーがよかった。洗濯だってたまっているし、明日も早い。それなのに。
「仕方ないのう」
という答えしか持ち合わせていない自分を呪った。それを聞いたパウリーが、よし! 決まりだな、歯を見せて笑い、先に立って歩く。その背中を追うように、家とは真逆の方向に重い足を引きずった。
「ところで金はあるのか?」
店は相談せずとも決まり切っていたので、三人とも同じ方向に歩を進めていた。夕陽はぐっと傾き、これから始まる夜の賑わいが顔を出し始めている。昼の騒がしさとは違う夜の浮ついた空気は実を言うと好ましく感じているが、口に出したことはない。
「おう、今日は勝ったからな!」
「今日『は』。相変わらずじゃのう」
『懲りないやつだ、ポッポー』
「うるせえな! 勝利の宴だってのに水差すんじゃねえよ」
パウリーが肩に回してくる腕の重さがやけに煩わしい。そもそも、この男は体温が高いのだ。触れている部分がじんわり熱を帯びていくのが鬱陶しくてじろりと睨むが、当の男はこちらの不機嫌さは露知らず。能天気に笑っていた。
気づかれぬように深くため息をつく。そうだ、こういう男だった。
足元から伸びた長い影は三人分くっついて一つの大きな生き物にみえた。好き勝手にくねくねと動くそれは、一部は自分の影なのに自分の意志とは違う動きをしているように見える。影は随分楽しそうだ。思ってすぐ、くだらない、と一蹴する。
「ええい、暑苦しい!」
『同感だ。さっさとこの腕を下ろせ』
「つれねェやつらだな! 今日は誰が奢ってやると思ってるんだ」
軽口をたたきあっている間に太陽は呆気なく沈んだ。あと三百六十五回。三百六十六回目の太陽はここでは見ない。だが、それまでは。きっと隣で。
おしまい



朝の光をまんべんなくうけた町はそれだけで美しい。外に出ると遠くで朝の七時を告げる音楽が鳴り始め、朝の調べと一緒に潮の匂いが風に乗って運ばれてくる。ストレッチと軽い朝食はすでに済ませた。いちに、いちに、と心のなかで反復しながら屈伸をしてから地面を蹴ると、たちまち空に近づけることを知っていた。いつもの屋根に見当をつけて、住民を驚かせないように、軽い軽い音を心がけて着地する。高所に行けば行くほど朝の空気は澄んでおり、自分を洗ってくれるような気がしている。海王類ほどに見える白い大きな雲が空を悠然と泳いでいた。
カク、と呼ばれ下を見やれば、笑顔の眩しい彼が片手をあげた。金髪が朝日にキラキラと溶けていきそうだった。おはようさん、と言いながら、カクは登ったばかりの屋根から飛び降りた。こんな朝早くから珍しいこともあるもんじゃ、とからかう。
「今日はあいつらが家まで押しかけてきそうだからな」
これも作戦のうちよ、と誇らしげなパウリーの言葉にカクは思わず吹き出した。『あいつら』とは金を借りている男たちのことだろう。金を返さずに悪びれぬ彼だが、どこか憎めないのをカクは知っている。朝飯は? と問うと、いやそれがよう、と口をもごもごさせるので、食べ物もとい金が無いのだとわかった。
「仕方のないやつじゃのう」
「さすがカク様! ありがてえ、ありがてえ!」
「まだ奢るなんて言っとらんじゃろ……」
「なに!? 奢ってくれんのか?」
というパウリーの言葉に、しまったと口に手を当てるがもう遅い。カクはため息をつきながら、朝からやっているいくつかのカフェのうち、一番安く済みそうなカフェの名を口にした。
日差しが肌をじりじりと焼くのも、首筋を伝う汗がタンクトップを湿らせていくのもいとわず、黙々と作業に没頭する。昼の十二時を知らせるチャイムが鳴ってもパウリーの手は止まらなかった。咥えた葉巻はもう大分短い。今日は風がなかったので、葉巻からの煙はゆらゆらと彼の周囲に停滞し香りだけを残してゆっくりと消えていく。手元を見る彼の視線はまるで光線のよう。今日の強い日差しと相まって、見つめるその一点を焦がしそうなほどだった。
それを阻止したのは一枚の濡れたタオル。顔面にぶつけられたそれは、さすがに彼の手を止めた。ぶわっ、という声とともに短くなった葉巻がじゅっと音を立てて消える。煙も吹き飛び、心なしか彼の輪郭がくっきりとする。
「おいこら! なにすんだ!」顔を覆ったタオルを取り開けた視界の先にいたのはルッチだった。
『お前のその集中力は唯一称賛に値する点……だと思うこともなくはないが、度が過ぎる。もう昼だ。生産性が落ちるから休憩しろ』
「素直に褒めらんねェのか、お前は」
言いながらカクの姿を探す。いつもならルッチの隣で早くしろと飯をせっつかれるのだが。
「カクは?」
『今日は食いたいものがあるからと一人でどこかに行った』
逃げたな。カクの奢りで朝食を頬張ったパウリーにはカク不在の理由がピンときて、何気ない風を装いながらルッチに探りをいれる。
「へえ、珍しいな。じゃあ今日は二人か。どうする?」
『何か食いたいものがあるのか?』
「今日は外に食いに行こうぜ」
社員食堂では、給料から天引きされる。外の店で腹いっぱい食べたあと、ルッチに泣きつけば、ルッチも奢らざるを得ないだろう。
『わかった。いいだろう』
カクからは何も聞いていないらしい。あいつのことだ、ルッチも同じ目に遭えばいいと思っているに違いない。パウリーはカクの期待に応えるべく、ルッチと肩を並べ会社近くの食堂に向かう。
彼は今日は何を所望するだろう。コーヒーか、そろそろ紅茶か──。カリファの熟考を三時のチャイムと電伝虫の呼び出し音が砕いた。受付からの用件を聞きながらそっと窓の外に目をやる。
「アイスバーグさん」
「ンマー、なんだ?」
「また、あのお客様です」
カリファがそう告げると、アイスバーグはカーテンの隙間から自分がさっきしたのと同じように窓の外を盗み見た。玄関先にコーギーの部下たちがたむろしているのをみて、あからさまにげんなりしている。
そんなに辛いのなら、さっさと手放せばいいものを──この人は社長でかつ市長でもあるのに、実に表情が豊かだった。だが、壁に貼った手配書走らせた一瞬の視線は険しい。それが何を意味するのかまでは決して悟らせない。そういう人だ。
持っているならはやく手放して。心に思うだけで決して言わない言葉が、カリファの胸に澱のようにたまっていく。傷つけたいわけではない。目当てのものが手に入れば私達は黙って姿を消すだけ。だから、はやく。
そこまで考えて、軽く首を振る。彼はたとえ私が正体を明かして説得したところで態度を変えないだろう。どんな忠告も懇願も彼には届かない。それなら。
「コーギー氏とお会いする前に、何かお飲み物でもいかがですか?」
「それもそうだな。今日は紅茶に」
「淹れてきました」
さすがだな! という称賛を得て、顔がほころぶのに気づいたカリファは、そっと眼鏡をかけ直した。
最後まで優秀な秘書を全うするまでだ。
細い細い月が水の都をそっと照らしている夜のこと。海を帯びた生ぬるい夜風が、月明かりも届かぬその場所を通り抜けていく。
誰にも知られていない四人は、誰にも知られてはならない会話を続ける。
「準備はいいか?」誰かが問う。
「問題ない」低い声が響く。
「天気も上々」少し若さの残る声で返答がある。
「ちょうど新月」しっとりした声が提案を後押しした。
「それならば──」最初の声が言う。
「明日、頂こうか」
湿った黒い風がごうと吹き、車両基地に戻る海列車の汽笛がのどかに鳴った。なんでもなかった、いつもと変わらぬ一日だったはずの今日が、この瞬間からたちまち襲撃前日に、そして潜入任務最終日となる。
ある晴れた日のことだった。
おしまい