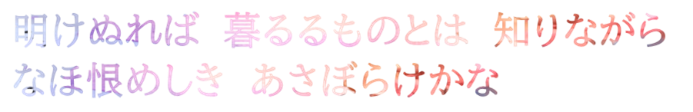それでも愛しいあさぼらけ
あさぼらけ、っていつのことだったかな、とは言った。カクが、わしは聞いたことないのうと首を傾げると、ああ生まれた島の、古い言葉かもしれないとがはにかむ。
事を終えたあと、軽くシャワーを浴びた二人は、疲れてそのまま寝てしまった。今日は朝から静かな雨が降るという。ならば部屋でのんびり過ごそうと決め、食材も買い込んでいたので、このまま二度寝もやぶさかではない。
カクがを見やると、は目を開けてこちらを見ていた。甘く絡みついてくる視線が気恥ずかしく、カクは「そんなに見つめんでくれ」とそっぽを向いた。ごめんごめん、なんかかわいくて、というの気さくな謝罪を後頭部で受ける。
三年前・初夏
私の島には短い詩を読む文化があってね、とは寝るつもりがないらしい。カクも、どちらでもよかったので、またに向き直り、ふんふんと相槌を打った。
「あさぼらけって、その短い詩で使われてた言葉だった気がする」
「へえ、どんな詩なんじゃ?」
ちゃんと覚えてないんだけど、あ、この詩はね、リズムが大事なの。古語だから伝えるのが難しいなあ、ちゃんと覚えておけばよかった、は悔しそうに言った。
「確か、夜が明けたらまた必ず日が落ちて夜になる。そうすれば、またあなたに会えるとわかっていても、それでもやっぱり、夜が明ける、あさぼらけは恨めしいなあ、みたいな」
言いながら、あ、思い出した、とは詩を詠じた。
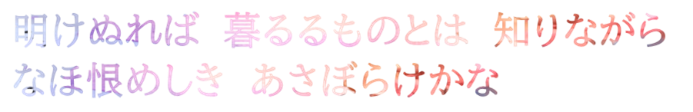
「あけぬれば」だとか「くるる」だとか、聞いたことのない言い回しもあるが、口に出すと確かにリズムが小気味よい。
「なんで夜しか会えんのじゃ?」
「大昔は、男の人が女の人の家に通うスタイルだったんだよね。で、結婚してない男女は夜しか会えないんじゃなかったかなあ」
「へえ」
は、適当でごめんね、あんまり自信ない、と苦笑いした。
カクは言葉にしなかったが、理由は違えど自分も似たようなものだなとそっと思う。カクはを自室に招くことはほとんどなかった。がそれをどう思っているのかはわからない。自室で何かを悟られるへまをするつもりは毛頭なかったし、パウリーが訪ねてくることだってままあったが、を頻繁に出入りさせるのは少しだけ気が引けた。
それは、カクの部屋が仮の住処だったからだ。この「巣」はいずれ、からっぽになる。そんな場所にを置いておきたくなかった。もちろん、来たいと言われれば断るつもりはない。ただ、幸いなのか、からカクの部屋に行きたいとは、ほとんど言われなかった。理由は聞いていない。でも、それに甘えてカクはの部屋に入り浸っている。
「大昔じゃなくてよかった」
こんな時間にカクが帰ったら、寂しい。が子供みたいな素直さで呟く。カクは何も言わずを抱き寄せて、の頭を撫でるようにしながら、髪を弄んだ。しっかりと乾かさないで寝たせいか、後頭部のあたりがひどいことになっている。何度も指を滑らせ、絡んだ髪を少しずつ梳いていく。
「どこで習ったんじゃ?」
「習ったっていうか、小さい頃、おばあちゃんに聞いたんだったかなあ?」
家に詩集みたいなものがあってね、古くてね、とは思い出の中の詩集を開いていた。そうか、とカクが言葉少なになると、がおずおずと尋ねる。
「カクは、どんな子供だった?」
「ええ? どんな……、そうじゃのう、」
カクは内心、普通とは明らかに違う子供時代をどう説明すれば違和感がないかと頭を巡らせた。訓練に明け暮れた日々の大半が、人においそれと言えるようなものではなかった。「世界を守る」ための技術と教わったが、自分に課された任務の大半は「壊すこと」だったなと思い返す。
あの不自由で窮屈な、矛盾だらけの世界でなんとか上り詰めた結果、自分は今こうしてあたたかいベッドに半裸で寝そべっている。なんだかなあ、と苦笑した。
そして、下手な嘘はつかず、言えるところだけ真実を言おうと決めて口を開く。
「優秀な、子供じゃったな」
「パウリーみたいなこと言うね」
がああ、おかしい、とケタケタ笑い、でもカクならきっと本当だね、と目尻の涙を拭った。パウリーと並べられるのは心外だったが、仕方ない。パウリーは嘘じゃろうけど、わしはくだらない嘘はつかん、と本当のことを言った。そう、必要な嘘しかつかない。
「船大工にはその頃からなりたかったの?」
「そうじゃのう、船は好きじゃった。でも、なれるとは思っとらんかったなぁ」
「なんで?」
「わしは、別の仕事をするんじゃと思っておった。好きなことではなく、得意なことを」
「得意なこと?」
「まあ、解体、じゃの」
嘘は言っていない。
「カクは、解体は好きじゃなかったんだね」
「そうじゃのう。ただ、大人には褒められた。じゃからきっと、そういう仕事をするんだと」
には以前、親の顔は覚えていない、幼少期にはあまりいい思い出がない、と伝え、悲惨な幼少期を匂わせている。案の定、は深くは聞いてこなかった。代わりに、
「才能、得意なことが道を決める、ってこともきっとある」
って、私の好きなスパイの本に書いてあってね、とカクをまっすぐ見据えた。
カクは眉をぴくりと動かすことも、冷や汗をかくことも、心拍数があがることももちろんないが、それでも腹の中で、どきり、とした。
「確かに、まあ。得意なことで食っていくのが効率がいいし、ストレスも……ないだろうしの」
「その本は大好きだし、得意なことがない私にはかっこよく思えた言葉でもあるんだけど、でも。私、最近泳げるようになったでしょう? 苦手だけど、上手じゃないけど、好きなの。泳ぐの」
だからさ、とは続ける。
「得意だからってやらなくてもいいよね」
「え?」
の言葉に耳を疑った。それは、子供の自分が欲しかった言葉。
物も人も、壊すのは嫌いだったが、得意だった。大人が褒めるから、続けた。それに、それが出来ない子供たちは一人、また一人、と顔を見せなくなった。だから、続けた。
が手を伸ばして、カクの髪を梳く。そうして頭を両手で包むようにすると、顔を近づけて、瞼の上にそっと唇を落とした。しっとりとした熱が薄い瞼に残る。
「私、もし小さなカクに会えることがあったら、絶対言ってあげたいの。好きなことも、していいよって。あなたは大きくなったら船大工になれるよって」
絶対言うからね、とは力強くこぶしを握る。カクは、怖がって逃げんようにせんとな、と頬を緩めた。
子供の頃にそう言われていたら、カクはおそらくここに、半裸でベッドに寝転んではいないだろうなと思った。きっと船大工にもなれなかった。どちらが幸せなのか、カクにはまだわからない。ただ今は、こっちの道もそう悪くないのではないかとうっすら思っている。
「好きなこと、か。わしも『これ』は、大人になってから好きになったのう」
カクがの鎖骨を肩の方から中心に向かって指でつ、となぞる。真ん中まで来たところでそっと下に指を滑らせると、膨らみの谷間、みぞおちあたりまで指を運べるが、さすがにそれ以上はキャミソールの襟ぐりに邪魔され進めない。無理に引かれたキャミソールがの双丘に張り付いて、かえって覆っているものの存在感を示した。
「好きなことは、していいんじゃろう?」
「そういう言い方は、してないけ、ど……ッ」
カクは、の瞳に、耳に、頬に、吐息に、熱がこもっていく、この瞬間が好きだった。
「大昔じゃなくてよかった」
夜も昼も関係ない、とカクが悪戯っ子のように笑うと、それもちょっと違うんだけどな、とが言いながら、観念したように舌を絡めはじめる。
prev
top
next